「言葉にならない気持ち」と依存症~話すことから始まる回復~
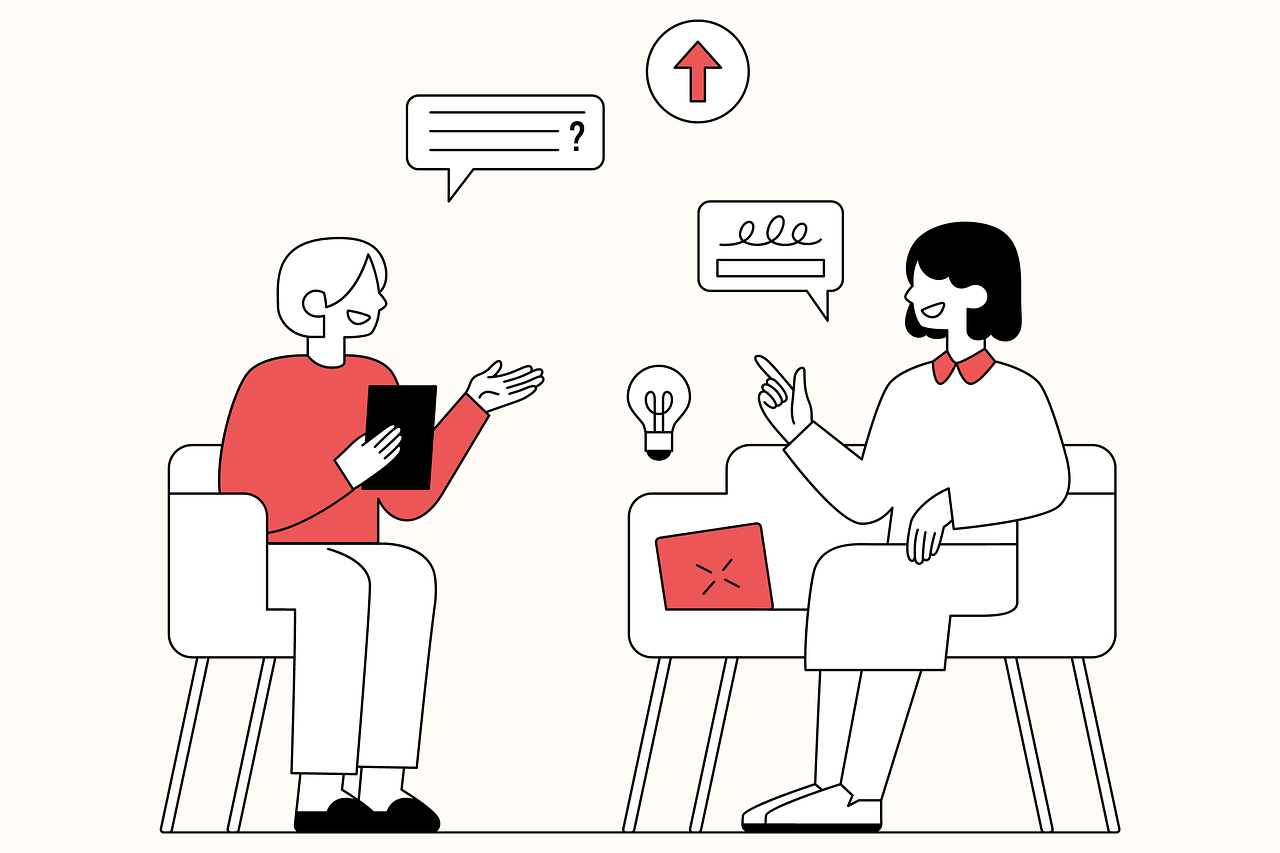
目次
はじめに:言葉にならない苦しみを抱えて
「どうしたの?」と聞かれても、なんと答えていいかわからないことはありませんか。
本当はつらいのに、うまく言えない。何を感じているのか、自分でもよくわからない。そんな自分を責めてしまうこともあるかもしれません。
私自身、カウンセリングの中で「うまく話せないんです」「何を言いたいのかわからない」と戸惑う方にたくさん出会ってきました。
でもそれは決して特別なことではありません。むしろ、多くの人が感じている自然なことです。
このコラムでは、「気持ちを言葉にすること」と依存症の関係について、やさしくお話ししてみたいと思います。
言葉にならない思いを抱えたまま苦しんでいるあなたが、「話してみようかな」「誰かに聞いてもらってもいいかもしれない」と思えるきっかけになれば嬉しいです。
気持ちを言葉にするってどういうこと?
「気持ちを言葉にする」というと、「楽しい」「悲しい」と言うだけのことだと思うかもしれません。
でも実はもっと深い意味があります。
私たちは日々、いろいろな感情を感じています。でも、それらはいつもはっきりした形をしているわけではありません。
「なんとなくもやもやする」「胸のあたりがざわざわする」「何か不安だけど理由はわからない」。
こうした曖昧な感覚(フェルトセンス)を、「これは寂しさかもしれない」「不安だったのかもしれない」と言葉にしてみる。
それが「気持ちを言葉にする」ということです。
心理学ではこれを「感情のラベリング」と呼ぶこともあります。
言葉にすることで、自分の内面を少し客観的に見ることができ、頭と心の間に距離が生まれます。
その距離が、感情に巻き込まれすぎることを防ぎ、落ち着きを取り戻す助けになるのです。
でも、実際には「そう簡単にできない」と感じる方も多いでしょう。
次は、その理由について考えてみたいと思います。
言葉にするのが苦手なのには訳があるかもしれない
子どものころ、「泣くのは恥ずかしいこと」「怒るのは悪いこと」と言われた経験はありませんか。
もしくは、親が忙しかったり、感情を表に出さない家庭で育ったりした方もいるかもしれません。
そういう環境で育つと、自然と「感じないようにする」「話さないようにする」ということを覚えます。
これは心を守るための大切な仕組みでもあります。
悲しみや怒りを感じないようにすることで、つらさをやわらげようとしていたのです。
また、学校や社会の中でも「空気を読む」「我慢する」ことが求められる場面は多くあります。
そうして「本当の気持ちは言わない方がいい」と感じるようになると、やがて自分でも何を感じているのかわからなくなってしまうことがあります。
これは決して「心が弱いから」でも「努力が足りないから」でもありません。
むしろ、生き延びるために身につけた大事な力だったのです。
でも大人になった今、その力が「生きづらさ」の原因になってしまうこともあるのです。
言葉にならない気持ちが依存症とつながるとき
気持ちを言葉にできないまま心に抱え続けると、その苦しさはとても大きくなります。
「なんとかこのつらさを感じないようにしたい」「考えたくない」という思いから、人は別の手段を探します。
アルコールや薬物、ギャンブル、過食などは、そのつらさを一時的に麻痺させてくれる道具になります。
飲んでいる間、賭けている間、食べている間は苦しい気持ちを感じなくてすむ。
でも終わったあと、気持ちはまた戻ってきてしまう。そして自分をさらに責めてしまう。
依存症は「意志が弱いせい」ではありません。
むしろ「気持ちを言葉にできない苦しさ」「感じることのつらさ」と深くつながっています。
感じたくても感じられない、言いたくても言えない。そんな心の叫びが、行動として表れていることもあるのです。
依存症の回復と「言葉にすること」
では、どうすればいいのでしょうか。
依存症の回復の中では、「言葉にすること」がとても大きな役割を持ちます。
たとえば、自助グループで自分の体験を話してみること。
安心できる相手や信頼できるカウンセラーに気持ちを聞いてもらうこと。
最初は「何を話していいかわからない」「うまく話せない」と感じるかもしれません。
でも大丈夫です。「話す内容がまとまっていない」と感じても構いません。
むしろ、それこそが今のあなたの正直な姿だからです。
そして誰かに聞いてもらうことで、「言ってもいいんだ」「わかろうとしてもらえるんだ」という安心感が生まれます。
それは、自分の気持ちを少しずつでも言葉にしていく力を取り戻す大きな助けになります。
完璧じゃなくても大丈夫
多くの人が「きちんと話さなきゃ」「うまく説明しなきゃ」と思ってしまいます。
でも本当に大切なのは、完璧に話すことではありません。
「よくわからないけど、苦しい」「何を言いたいのか自分でもわからない」でも大丈夫です。
「言葉にならない」ということ自体を、そのまま言葉にしてもいいのです。
そうやって話しているうちに、少しずつ心の中のモヤモヤに形が見えてきます。
気づかなかった気持ちに出会えることもあります。
言葉にすることは練習です。すぐにうまくできる人なんていません。
大事なのは、少しずつでもやってみようと思うことです。
試してみようと思えたあなたへ
もし今、「話してみようかな」と少しでも思えたなら、それはとても大きな一歩です。
自助グループは、同じような経験をした人たちが集まり、お互いの話を聞き合う場所です。
話すのが苦手でも大丈夫です。最初は聞くだけでも構いません。
カウンセリングは、専門家と一緒に気持ちを探していく場所です。
「何を話していいかわからない」と最初に伝えるだけでもいいのです。
どちらも「あなたがどんな気持ちを持っているのか」を大切にしてくれる場所です。
「聞いてみるだけ」「一度だけ試してみる」でも十分です。
無理のないペースで構いません。
おわりに:言葉にすることは、自分を大切にすること
気持ちを言葉にすることは、自分の心の声を大切にすることでもあります。
「こんな気持ちは感じたくない」と思っていた感情にも、「いていいんだよ」と言ってあげることです。
たとえ今はまだ言葉にならなくても、「私は何を感じているんだろう」とそっと問いかけてみてください。
それだけでも、自分を少しずつ理解し、いたわることになります。
あなたの声は、必ず誰かに届きます。そして何より、自分自身の心にも届いていきます。
どうかそのことを信じてみてください。


